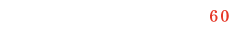水産養殖の自動化を目指すウミトロンは、やがて訪れる「タンパク質不足の時代」に挑む
世界の人口は、2050年に97億人に達すると言われている。人口増加に伴い、生命維持に必要なタンパク質の需要が高まると予想されているが、牛・豚・鶏などの家畜を増やそうにも、家畜が必要とする飼料の耕作面積や単位あたりの収穫量には限界がある。
魚はどうだろう? 世界の食用魚介類の消費量が増加する一方で、気候変動や漁獲により、水産資源は減少しているのが実状だ。
人類は、「タンパク質不足」という深刻な社会課題に、どう立ち向かえばいいのだろうか。この課題の解決を試みているのが、ウミトロンだ。
同社ではIoTや衛星データ、AIなどを活用し、水産養殖の自動化を目指している。Co-founder兼最高経営責任者(CEO)である藤原謙に、その取り組みを訊いた。
「わたしたちの多くは、今後もこの惑星で生活し、進化を続けていかなければなりません。しかし、資源は限られています。土地の利用には限りがあり、陸上では耕作面積は頭打ちになりつつあります。単位面積あたりの収穫量は、テクノロジーを駆使しても2倍に増やせればいいほうではないでしょうか。一方で、海では沖合を含めて養殖をすれば、世界の水産物消費量に対してまだ100倍は生産量を伸ばせるポテンシャルがあると言われています」

青:水産養殖のポテンシャルが高いとされる場所。赤:ポテンシャルが高いとされる上位20パーセントの場所。生育可能な魚種やそれに適した環境、水深などが組み合わされてポテンシャルが算出されている。IMAGE BY UMITRON, Rebecca R. Gentry,et al., Mapping the global potential for marine aquaculture, Nature Ecology & Evolutionvolume 1, pages1317-1324(2017)
生産現場を圧迫する“餌代”
これまで養殖業界には最新のテクノロジーがほとんど導入されることはなく、1970〜90年代にかけて導入されたオペレーションがそのまま続いている場合も少なくない。養殖業を発展させるには、海の性質を精緻に把握することはもちろん、遠隔でも安定的に魚を育てられるテクノロジーが不可欠となる。
宇宙航空研究開発機構(JAXA)の元エンジニアだった藤原は、かねて衛星データと一次産業の接点に着目し、テクノロジーを用いて水産養殖業界を改善できないかと考えた。
ウミトロンがまず目指すのは、餌やりの効率化だ。餌やりは、コストや労務、環境負荷などのあらゆる課題に関連する。餌代は、ここ15年で3倍ほど値上がりし、養殖現場の生産コストの6〜7割を占めているという。背景には、餌の原料となる魚粉、つまり小魚の乾燥粉末の価格高騰が関係する。
また、天然魚の乾燥粉末は海の天然資源を利用しており、環境負荷も高い。ほかにも、魚が残した餌が海の底質環境を悪化させるなどの課題が挙げられる。さらに、雨でも雪でも、1日に何度も餌やりのために沖に出る必要があるとなれば、その労務環境は過酷極まりない。つまり、餌やりを効率化できれば、同時にさまざまな課題を同時に改善できるのだ。
その他の業界情報
当店のご利用について
当店では、一般のネットショップと違い、直接お客様とコミュニケーションを取りながら、その日の美味しい魚達をご提案させていただいております。
お電話、メール、LINEにて簡単にご利用いただけます。
- 06-6643-3332受付時間 9:00~18:00(日曜、祝日休み)
- お問い合わせ